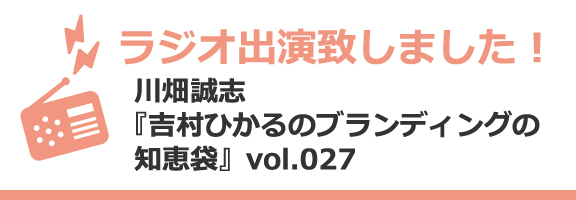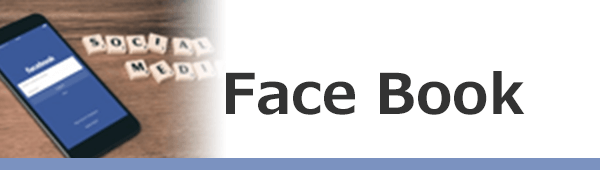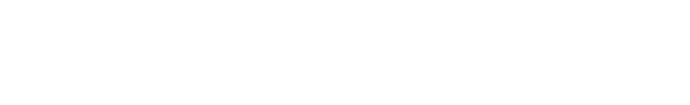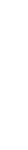ものづくり学校、寺子屋、工房を主宰する井上由季子さん。
香川県三豊市を拠点に、病院内でのものづくり、デザイン等に関する活動を行う。
井上さんの称する「創造的ケアの試み」について知りたくなって、話を聞きに三豊市へ行った。
四国こどもとおとなの医療センターに展示されたアート作品
井上さんの『大切な人が病気になったとき、何ができるか考えてみました』は、「親の気持ちや希望を看護師や医師にわかりやすく伝えるにはどうしたらいいか」が具体的に綴られており、デザイナーとして関わった病院でのもの作りについても綴られている本だ。
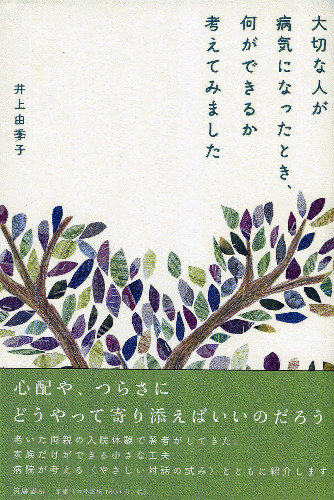
その本に登場する、四国こどもとおとなの医療センター(香川県善通寺市)。
井上さんのもとを訪ねる前に、医療センターに立ち寄った。一言で表すならば「やわらかい病院」だった。
四国こどもとおとなの医療センターは、ホスピタルアートを導入しており、例えば小児病棟の廊下には誰でも受け取ることのできるギフトが入った扉、花、アート作品が並ぶスペースがある。
8月上旬、棚に展示されているアート作品はセミとトンボ。
このアート作品に携わっている井上さんは「病院に虫はいませんが、心だけは病院から抜けられるように意図しています」と説明する。
外では今、どのような自然が感じられるのだろうか。
春であれば桜などの花が、夏であればセミが鳴いている。秋なら、冬なら…。
こうしたアート作品を見て「あっ!」と思う。その瞬間、心は”今の自然“に向かう。
変化のない、殺風景になりがちな病院を抜け出す。
「“普通の日々”を棚に再現できたらと考えているのです」
親の入院、介護での“工夫”
井上さんには親の入院、介護経験があり、そこでの工夫や試みは、井上さんならではの気づきやアイデアに満ちている。
著書にも書かれているが、それが後の病院でのものづくりの活動にもつながっていった。
家族の気持ちや要望をポスターや張り紙にして掲示する。
ベッドのうえで寂しさを感じないように、ティッシュの箱に家族写真を張ったり、家族写真をプリントしたTシャツを飾ったり。
それらは自ずと医療関係者との円滑なコミュニケーションにもつながったのだ。
「母の在宅介護をしていましたが、仕事が忙しく、なかなか会えないケアマネやヘルパーさんに、母の要望をどう伝えようかあれこれ考え、ファックスを送り続けていました」
要望だけではない。
近況報告も含め、細かく送っていたという手書きのファックス。
介護事業所はファックスをファイリングしてくれていたという。
手書きというアナログさで、より伝わりやすかったのかもしれない。
大切なコミュニケーションツールになっていた。
7年半に及んだ母親の在宅介護。
「ケアマネさんやヘルパーさんとのチームプレーで在宅介護ができました。“ともに”どうしたらいいか、考えることができました。大切なのは“ともに”という姿勢なんですね」
好きなこと、のチカラ。自分らしさをノックする
「親のことも含め、人は病気になっても自分にしかできないこと、好きなことを形にすることの大切さを身に沁みています」
”親“というのは、井上さんの、特に父、義母のことだ。
井上さんの母親が介護施設に入所した際、自宅で一人きりになる父を心配した井上さん。
当時79歳、趣味がなく、“ヘンコツ”(偏屈)な父によい刺激になればと勧めたという魚の切り紙。
紆余曲折ありながらも切り絵にハマっていき、メキメキと腕を上げていったという。
最終的な魚の切り絵のノートは169冊にも及んだ。
そのことは『老いの暮らしを変えるたのしい切り紙』に綴られている。

井上さんが父に切り絵を勧めるきっかけになったのは、義母がもともと楽しんでいた、包装紙や他の紙をソックス型に切ってノートに貼る“靴下の切り紙”だった。
井上さんと現在も共に暮らす義母はソックスベアの提案者。
これまでに500体以上ものソックスベアを製作してきた。
90歳ながら、NHKにも出演するほどのパワーの持ち主だ。
そんな義母の”靴下の切り紙“も、主宰するものづくり学校の宿題を義母が見て「面白そうね」と始めたもの。
「ものづくり学校やワークショップでは、何かを専門的に教えるのではなく、その人らしさを大切にしています。私は先生ではありません。私が感じた本当のことを言葉にして伝えるだけ。感想を言うだけなんです。自分を客観的にみる機会は普段なかなかありません。きちんとカタ通りに進めるのが日本人気質で、カタからはみ出たモノが好まれない傾向もあってでしょう。ものづくりを通し、その人らしさが感じられたらそれを伝える。そうして自分の個性に気づいていくんです」
井上さんは、「自分らしさをノックするものづくり学校」とも表現する。
介護施設でのワークショップ
モーネ工房として、大阪のデイサービスで新聞紙を素材にカレンダーを作るワークショップを定期的に開催してきた。
「“上手にしないと”と職員さんは手を出しがちですが、次第に見守ることができるようになるんですね」
体の状態によって利用者さんの出来ることもそれぞれ。
はさみを持つことができなければ好みの色を選んでもらえばいい。
「アジサイを作ろうとしたとき、紫色のカーディガンを羽織っている人であれば紫色の紙を選んだり、その人の思い出で切る紙を選んだり、紙の選択にも“人となり”が現れる。心動いたものを人は選ぶ。いつも真実を探し、言葉にして伝えようと心がけています」
ワークショップを終えると「切り紙って心で切るものなんやね」「人それぞれでいいんやね」といった感想が聞かれるという。
「まるで絵画のように紙を切り貼りすると思っていたら、昔、絵を描いていた人だったり。”教えない“ことで個性がにじみでてくるんです」
上手、でなくていい 個性引き出す新聞活用
意識するのは、切り絵ではなく、切り紙だということ。
井上さんが切り紙で使用するのは主に新聞紙。
「新聞紙だと色むら、模様、色使いも様々。新聞紙は柔らかいため手でちぎれるのもいいんです。手を動かし慣れていない人も入りやすいのが新聞による切り紙です」

例えば、スイカの切り紙をするとなった場合、「スイカに見えなくては」と、あるいは「上手に見えなくては」と、スタッフは手を出してしまいがちだ。
「『うまいね』『きれいだね』といった声掛けは、実は見ていないからこその言葉だと思うんです。
手助けしてしまうと、みな同じものができてしまうんです。
施設の管理栄養士がスイカの作品を見たとき『美味しそうな色やね』と言葉を漏らしたのですが、それは作品と真剣に向き合ったからこその言葉だと思います」
“みな同じものができてしまう”。
普通の色紙であればなおさらで、それが高齢者施設で言われがちな“幼稚な印象”にもつながっているのかもしれない。
色紙は、色の数に限界があるが、新聞紙にはバリエーション豊かな色がある。
それは様々な人生経験のある高齢者が、豊かな表現の切り紙をするのにも持ってこいなのだ。
デイサービスでは作業療法士的観点で、新聞紙の色分けトレイを作り、色分けを利用者がしていたり、色の分別もわかりやすい表示があったりと、井上さんが驚く工夫も多かったという。
従来、色紙で作成していた施設の壁画が新聞による切り紙の作品に変わった。
「利用者の方の腕が上達していき、壁画も感動してしまうほどの作品になっていきました」
切り紙が、巧みな技を持ったものへと変化した。

「ワークショップを開催する先々で、『利用者(患者)さんへの言葉がけが参考になります』とよく言われるんですよ」と井上さんは笑う。
「私が感じた本当のことを言っているだけなのですが、上辺だけの『きれいですね』『上手ですね』ではなく、ここがこう思った、などという本当の言葉こそが届くのでしょう」
言葉が届き、納得し、ゆるむ。深いコミュニケーションへとつながっていく。
アートとは、ワンウェイ、一方通行なものが多いが、井上さんの取組みは、“ともに”という姿勢を外すことなく、相手と自分とを行ったり来たりするコミュニケーションとしてのアート、あるいはデザインの活用だ。
創造的ケアとはなんだろう
井上さんは、病院等でのものづくりやワークショップの活動を通じて、得るものがとても多いと話す。
「自分の知っている範囲内だけで活動していたら、あのような(四国こどもとおとなの医療センターにある)作品は生まれなかったと思います。気付かせてもらうことが本当に多いです。医療センターにはいろんな人が関わっています。ボランティアとしてサポートしている人も多い。ともに喜び、感じあえる場。勉強させてもらっています」
井上さんの話を聞いていると、豊かさとは、“ともに”というところに存在、あるいは育まれていくものなのかもしれないと感じた。
気づきの多い場所には、豊かさのカケラが散らばっているのかもしれない。
あるいは、気づきの多い人には、豊かさのセンスが詰まっているのかもしれない。
―創造的ケアとは、ものづくりを通じた、その人らしさの表現、また、人との豊かなコミュニケーションそのもの…だ。