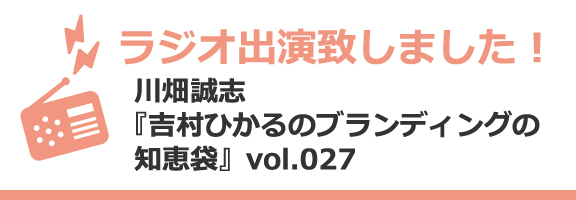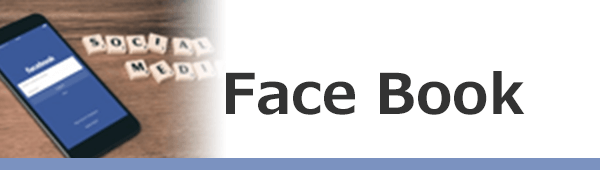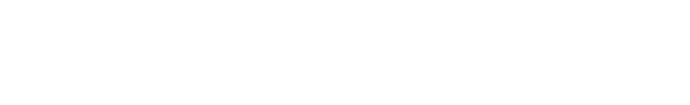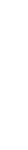神戸市長田区にある六間道商店街。この近辺には韓国人など外国人も多く暮らしており、雑多な雰囲気もあるまちだ。そんなまちにあるのが多世代型介護付きシェアハウス「はっぴーの家ろっけん~希望溢れる世界旅行の船旅へ~」。
ここは、乳幼児から子育て中の若い女性、外国人、認知症の高齢者まで、日々色んな人で賑わっている。
運営するHAPPPY(同)の代表・首藤義敬さんに話を聞いた。
地域に必要なものとは 問いかけから始まった
空き家再生事業など「ハコに合ったことを柔軟にやる」という活動をしていた首藤さん。
それは「暮らしを創る」ということだったという。
かつて一緒に暮らしていた祖父は事業家でもあり「家にいきなりブラジル人を泊めるような変り者でした」と話すが、首藤さんにとってその経験は今につながっている原体験の一つだ。
その後、阪神淡路大震災が起き六間道から人が消え、祖父の事業の閉鎖も決まった。
「家族の関係性が揺らぎ、僕も六間をしばらく離れていたんです。結婚が決まり、妻とともに両親や親戚、15人で暮らすようになり、大人数で暮らす良さに気づいた。はっぴーの家に集まる人たちは認知症高齢者、若い子育て世代など、言ってしまえば『社会的弱者』。でも、世代を超えて混じることで、時間も空間も様々なことをシェアするこの暮らしのなかで、メリットがあるんです」
独居高齢者が暮らす賃貸物件で家賃回収の仕事をしていた時、アルコール中毒の男性と出会い親交を深めていたが突然姿が見えなくなり、3か月後、車椅子に乗って現れたという。
「車椅子の状態でその賃貸物件で暮らし続けるにはリフォームが必要でしたがお金がない。施設に入るしかないという状況に虚しさを感じました。老人ホームは月額20万円ほどかかるところが多く、高額すぎると感じる高齢者は多いんです」
この出来事をきっかけに、はっぴーの家のプロジェクトが始まった。
地域住民などに「高齢者向けの建物がここに建ちます」とは言わず「ろっけんにあったら良いものは何ですか」と問いかけるワークショップを開催。
アイデアを集計・整理し、参加者に結果も配布していったという。
「一番多かった意見は『エンターテイメント性』だったんです。
だからここのコンセプトが世界旅行。マイナスを活かす、ということを考えた。
人生もう一度始まるよ、というメッセージも含んでいます。このあたりは外国人も多く、まちの雰囲気が『ガラが悪い』という見方もありますが、言い方を変えれば多様性があるということ。だから『世界旅行』とも言っている」
はっぴーの家の企画に1年半。
その模様はSNSで常に発信していたため、開設イベントには全国から400人もが集まったという。
「ゆるやかなコミュニティが地域を変えるんですね。自分たちのまちを作っているというモチベーションをどう上げていくか。やりたいことをやっているだけなのですが、結果的にワークショップで問いかけた『ここにあったら良いもの』のほとんどが実現できています」
「はっぴーの家」に看板はなく、1階は広い共有リビングになっている。

書棚、絵画、写真、ピアノ、卓球台…こういったもののほとんどが「誰かから贈られたもの」で「どれもストーリーを持っている」と首藤さんは説明する。
例えば卓球台は、学校に卓球部があるのをうらやましく思ったという男の子のことを地域住民が聞き、寄贈したもの。
その卓球台は子どもたちが使うだけではなく、日中はスタッフの「仕事デスク」として活躍している。

「今日は卓球大会があるし、また深夜0時まで賑やかになると思います」
ここの暮らしが合う人に入居してほしい 人の存在そのものが「はっぴーの家」をつくる
「ここの環境が必要な人に来てほしいから。月にひとりくらいのペースで入居してもらうのがいいんです。人の存在がコミュニティもシェアハウスもつくっていく。だから、その空気感を大切にしています」
居室の数は45。現在は20人ほどが入居しているという。
「1階は港をイメージして壁紙も選びました。港は出会いもあれば別れもある。様々なものが混じり合っているからこそ『雑多な長田港』といった感じです」
階段に使われている壁紙は黒板のような素材で何度でも落書きが可能。
子どもたちの落書きで溢れていて“楽し気”だ。
居室フロアは階ごとに「昭和」「アジアリゾート」「アメリカ」などのテーマに分かれており、2階の「昭和」には、黒電話や居酒屋の看板などが飾られている。

これらの小物は入居者や地域住民が持ち込んだものだという。
居室すべてに異なる壁紙が貼られているのも特徴的で「オウム好きのおばあちゃんのために用意した」という一面オウムの壁紙の居室があれば、4階のアメリカのフロアには、ヒョウ柄とキティちゃんが好きというヒョウ柄の壁紙の居室がある。
そんな居室をここで暮らす女性が快く見学させてくれた。
確かにヒョウ柄の壁紙。
部屋には幾つものキティちゃんグッズがある。窓は開けられ風が吹き抜けている。
そのおばあちゃんらしい空気感で満ちた部屋。心地よい暮らしの気配が感じられた。
「部屋作りは『私、この部屋キライ』を狙っているんです。奇抜でいい。誰か一人を狙っている。キライと表現する人がいるなら、大好きという人がいることだから」
お風呂が―、居室が―。
「設備が整っています、立派です」
そんなよくある“高齢者施設の宣伝”に飽き飽きしていたという。本人にとっての暮らしやすさが欠けているのではないかと首藤さんは指摘する。
「それぞれのフロアが今後どうなっていくかはわかりません。入居者が作っていくものだから、フロアに置かれる家具なども変わっていくでしょう。一人ひとり、みな考え方もあり方も違います。高齢者が暮らす場所の在り方にも正解はないと考えていますし、設備よりもその場所で、本人が日常をどのように暮らしていくのかが大切だと考えています」
外部にファンがいる “名物おばぁ”の存在
はっぴーの家には星ばぁという名物おばあちゃんがいる。
80代、認知症があり、気性も荒いのだが、今や外部にファンがいるほど人気者だという。
過去に工場でものづくりの仕事をしていたため、手先が器用なのだ。
賑やかな1階のリビングで、赤ちゃんの紙パンツのネーム書きやイベントで使う衣装作りなどに励む星ばぁの姿があるという。
「星ばぁは、自分の部屋に籠もり、静かななかで作業するというのではないんです。雑多な環境で作業をするほうが、かつての仕事の雰囲気と似ているのか、合っているようです」
新聞で作った星ばぁオリジナルのごみ袋は1枚50円で販売されてもいる。
「星ばぁとコラボしたいと、明石から若い女性が訪ねてきました。その作品をSNSで発信したところ、星ばぁの娘さんがコメントし、新たな出会いが生まれました」
入居者のファンがいる高齢者施設なんてないでしょう?と首藤さんは笑う。
首藤さんは株式会社HAPPYの代表でもある。
はっぴーの家の在り方は、会社のコンセプトのひとつ、「アタリマエをリノベーションする」ということの具体化でもあるという。
「会社のもう一つの理念は、“はっぴー”の総量を増やすことです。例えば、星ばぁのはっぴーを増やすにはということを考えたとき、星ばぁを特別扱いするのではなく、星ばぁに関わる人を増やすということを考えていく。もともと雑多な環境になじみのある人だから、外国人、地域の人、属性は問わない。程よい関係性をデザインし、全体のはっぴーを求めていくんです」
会社として訪問看護事業所も開設しており、今まで看取りも数件行ってきた。
「身寄りのない人も断っていません。赤ちゃんや子どもも多く訪れるから、孫のような関係性が築けます。こういう日常をみていいなと思う人に住んでもらいたいですし、もちろんここで亡くなってもいい」
一般訪問者が1週間に200名。
当然、ここで働きたいという人も出てくるため、求人を出さずとも自ずとクオリティの高いスタッフが揃った。
「資格の有無は関係なく、第一条件は人が好きということですが、はっぴーの家は人が好きでないと来ないと思うので、一次面接はクリアしているようなものです」
資格を持たずに経営 ぶれないビジョン
「素人でいることが重要だと思っている」と、首藤さんも首藤さんの奥さんも介護資格は持っていない。
「何がしたいか。はっぴーの家でしたいのは、長屋的な暮らしとコミュニティをつくりたいということ。ビジョンを明確にするのが僕の仕事だと考えているんです。資格を持ち、その資格の立場で物事を語ると次第に“したいこと”からずれていってしまいがち。コミュニティをつくることで、営業コストも下がるんです。地域の人が“あの人、ここに住んだらいい”と伝えてくれるし、言ってくれるので営業する必要もありません。また、SNSでの発信で生の情報は伝わっていますし、SNSでの評価は実名でリアル。何より、最終的に選ぶのは家族、本人でしょう」
首藤さんは続ける。
「僕たちが思っているよりも高齢者はキャパが広い。演歌だけでなく、新しい音楽も楽しんで聞くことができる。若者の好みにも対応できるんです」
今の高齢者は高度経済成長もネットやSNSの発展にも触れている。
そのため、入居者ははっぴーの家で日々行われるパーティーを楽しみ、外国人とのコミュニケーションも楽しむことができるのだという。
折り紙や塗り絵といった、介護施設で行われることの多いレクリエーションへの疑問が浮かぶ。
「本当はやりたくないかもしれない。お世話になっているから…と、我慢しているんじゃないかとも思うんです。介護業界は、B to B、すなわちケアマネと事業者との関係が第一で、ケアマネは自施設や営利関係のある施設を選んでもらうことを優先したり、同業者に気を遣っているなんておかしい。高齢者本人、エンドユーザーのほうに向いていないんじゃないか。暮らす場所を自分で選んではいけないのかと問いかけをしたくなる。暮らす場所を選ぶことと、自分の食事を選ぶことは同じではないでしょうか」
血縁より“タニン” 家族とは何か
はっぴーの家では夜間、シェアキッチンというものが行われているのだという。
「ひとり500円程度の費用で立派な食卓ができる。お母さんたちにとってはおしゃべりの場。子どもたちはここで自由に遊ぶことができる。親がその場にいないとしても、おじいちゃんやおばあちゃんと遊んだりすることもできる。人との触れ合いの場にもなっているんです。家族って何だろう、と問いかけてきました。今年は“遠くのシンセキより近くのタニン”プロジェクトというものに挑んでいます。入居者、スタッフ、地域の移住者、外国人…ここに集う人たちは誰一人血はつながっていません。でも、だからこそ、子育ても介護も成り立っているんです」
1週間にはっぴーの家を訪れる人の数は約200。これは関係人口の数字でもある。
今やどの市町村も移住者を求め、関係人口を増やしそうとしている。
移住者の増加、住民の増加につながるからだ。
関係人口が増えることで、子どもや高齢者の生活も確実に豊かになる。
それが、はっぴーの家で起きている。